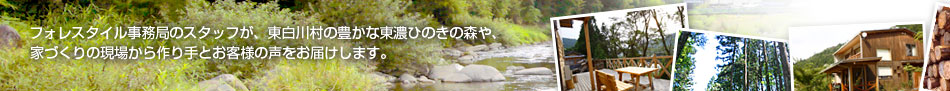匠たちの横顔|2010月05月20日
この度、「匠たち」の中でめでたく御結婚された方がいらっしゃいますので御報告させていただきます。
工務店・今井製材の今井治樹さんです。
モデルさんのようにスラリとしたきれいなお嫁さんを横に、幸せいっぱいの治樹さん。

おめでとうございます。
新婚旅行は、幸か不幸かアイスランド噴火の影響で足止めされてしまい予定より長めにヨーロッパに滞在されました。
バックパッカーの経験もある治樹さんは、あれこれと宿やチケットの手配に機敏に動き回られたそうで、さぞや頼もしかったことでしょう。
いつも穏やかに話され取り乱すことはなさそうな印象を受けますが、
さすがに、仕事については気がかりだったようで携帯電話で段取りされていたそうです。
なかなかサプライズなスタートをきったお二人ですが、どうぞ末永くお幸せに。
治樹さんは、宅建の資格もお持ちなので土地についての相談にものっていただけます。
今井製材さんのページはこちらから。
東白川村便り|2010月05月19日
東白川村では、この4月から「出産祝い金制度」がはじまりました。
第1子には3万円、第2子には5万円、そして第3子には10万円のお祝いがあるそうです。
昨日、村のCATVで第1号の贈呈の模様を放送していたのを、家族で見ていました。
すると、突然我が家の第3子の息子が
「ってことはなに? 僕は10万円でお姉ちゃんは3万円? そ~かぁ!」
と妙に喜んで確認していました。
あえて金額の格差の説明はやめておきました。
残念ながら我が家は出産金はもらえませんが、思わぬところで喜んだ人がいたので我が家にもありがたい制度でした。
これから出産を迎えるお若い方たちへ。
子育ては大変なようですが、第2子、第3子とだんだん面白くなりだんだんと楽に育てられるようになりますよ。
出産祝い金、どんどんもらってください。
花たより|2010月05月19日
前回紹介した花は、私が名前から知った花でしたが、今回の射干(しゃが)は、葉から知った花です。

冬でも葉が枯れないため、お花を習い始めた頃から、度々葉だけを使い、私には馴染みのある花材でした。光沢のある葉が印象的で、当時は、花のことまで気にかけていなかったような気がします。
射干(しゃが)とは、檜扇(ひおうぎ)の漢名を日本読みしたものらしく、葉が檜扇(ひおうぎ)に似ていることから、間違って名付けられたといわれています。中国原産で、かなり古くに日本に入ってきたものと考えられています。
湿った場所や薄暗い木陰などで群落を形成して咲き、どちらかというと地味で自己主張しない感じの花ではないでしょうか!?花はアヤメ科の中でも小振りです。一日花ですが、次から次へと咲く姿を見るとこの花の生命力を感じます。
花言葉は「決心、抵抗」そして「友人が多い」
フォレスタイルも射干(しゃが)のように友人がどんどん増えることを願っています。
花たより|2010月05月14日
私は時々、名前の響きから、花に興味を持ち、その花を知ることがあります。
今回紹介させていただく花もそのひとつです。
花筏(はないかだ)…ご存知ですか?
古風だけど、センスのいい素敵な名前だと思いませんか!?
名前に魅かれ、期待に胸を膨らませましたが、初めてお目にかかった時、「なにこれ!?」という感じでした。

それもそのはず…写真を見ていただければ、おわかりだと思いますが、普通の花とは、全く違った咲き方をしています。
花筏(はないかだ)は、雌雄異株の植物です。
写真は雄株です。
雄株の場合は、一葉に複数の花をつけますが、雌株は一葉に1個。稀に2~3個つけます。
葉の真ん中に小さな蕾みたいなものがありますが、それが花です。
若葉は山菜として、おひたしや佃煮として食べることができるそうですが、私はまだ試してはいないので、お味の事がコメントできないのが残念です。
花筏(はないかだ)という名前から綺麗な連なったものを連想していました。
実際には華やかさに欠けるところはありますが、葉に花を付けるという非常に稀な貴重な花だそうですよ。
花言葉は「嫁の涙」
花筏(はないかだ)には、こんな逸話があるそうです。
昔、若いお嫁さんが、お殿様から「葉に実のなる木を見つけて来い!」と命じられ、夜遅くまで山中を必死で探しましたが見つかりませんでした。
そして、悲しさのあまり、ついついこぼした涙のしずくが、葉の上に落ち、月の光に照らされて真珠のように輝きました。
けなげな姿は見習いたいですね。
花たより|2010月05月11日
何年か前に、ある茶室でこの花に会い、花の可愛らしさと珍しさに魅かれ、一枝分けていただきました。
場所が良かったようで挿し木で順調に成長し、今では高さが2mぐらいまでになり、今年もきれいな花が咲きました。

葉脈がへこみ折りたたんだようにくっきり見え、白花の清楚さが印象的です。
この花は、白花の山吹(やまぶき)のように見えますが、山吹(やまぶき)ではありません。
白山吹(しろやまぶき)といって、大変珍しい一属一種の植物です。
葉の大きさ、形が山吹(やまぶき)に似ていますが、白山吹(しろやまぶき)は花弁が4枚に対して、山吹(やまぶき)は5枚です。
花は数日で落ちてしまいますが、艶のある黒い実が4つ熟し、それが、来春まで残ります。
前年の実の脇に、今年の花が一緒に並んで咲いているなんて、なかなか他の植物にはない構図だと思いますが・・・。
花言葉は、「気品、薄情」。
白山吹(しろやまぶき)の花の見ごろは、あっという間で、薄情なようですが、黒いつやつやした実を見ると、そうでもないかな!?と思うのは、私だけでしょうか?!
花たより|2010月05月07日
1912年に、日本からアメリカへ友好の証として、桜を贈り、そのお返しとして、1915年に日本へ渡ってきたのが花水木(はなみずき)の始まりと言われています。

この話から、花言葉が「返礼」ということが理解できますね。
水木の仲間で、花が目立つことから付いた名前だということです。
花が、上向きに咲くのが特徴です。
外来種であるにもかかわらず、日本の風土に似合う和の上品さを感じさせ、見れば見るほど魅力ある花だと思います。
庭木の中でも、花よし、葉よし、実よしと三拍子そろった花木として人気が高く、近年ではあちらこちらで、色とりどりの花を見かけます。和風洋風どちらの家にも合うのでお奨めの庭木です。
日当たりと水はけの良い場所を好むようで、若木のうちは、幹がまっすぐ伸びて育ち、成木になると横に広がり大きくなる木ですが、好みの高さになったら主幹を切って芯を止めるという比較的簡単に管理ができるようです。
お好みの色で、シンボルツリーを1本いかがですか?!
匠たちの横顔, 東白川村便り|2010月05月06日
イベント情報でも告知しましたが、5月3日に「つちのこフェスタ2010」というイベントがありました。
絶好の行楽日和で、会場となった水辺公園は多くの人で賑わっていました。

気温もグングン上昇し、ツチノコの動きも活発になったはずでしたが。
残念ながら賞金121万円は来年に持ち越しになったようです。
「フォレスタイル」スタッフは、木造建築組合のブースでPRしました。
工務店さん11社も顔を揃え、お客様の対応や相談会などを行いました。
また、大工さんの作品の木工製品の販売も盛況でした。
テーブルセットや郵便受けなど、無垢の作品がとてもよかったです。
中でもブックエンドの組み立て体験のコーナーは待ち時間ができるほどの人気でした。

うちに遊びにきていたお客さんのお子さんは待ち時間が15分以上と言われ、お持ち帰りにしてました。
横浜に持ち帰り、ひょっとして夏休みの作品になったりして。
このブックエンドの製作者は村雲建設の村雲章さんです。

家具作りが得意で、お人柄はこの笑顔からも伺い知れます。 紹介ページはこちら。
それにしても、東白川の大工さんって本当に器用で尊敬してしまいます。
「こんな感じの棚、お願いしたいな」などとオーダーしてみてください。
きっと、どの大工さんも「よっしゃ」と返事が返ってくると思いますよ。
こういうのは、メーカーさんにはないメリットだと思います。
ご来場下さった方、ありがとうございました。
その他, 東白川村便り|2010月04月30日
いよいよGW突入ですね。予定はお決まりですか?
GWが終わると5月9日は母の日です。
母の日といえば、カーネーション。
実は、東白川村でもカーネーションの生産がされています。

ビニールハウスの中できれいに咲いていました。
先日「母の日に秘められた思い」という新聞記事を読み、 この花への思いが変わりました。
母の日が設定されたのには、諸説があるようですが、その記事は米ウエストバージニア州の話。
戦争中、いつか母親たちがたたえられる日が来るだろうと力を尽くした人を偲んだ逸話でした。
母の日にカーネーションを贈るようになったのは、その由来となった人が好きな花であったこと。
また、枯れても花弁を落とさないことから「この世を去っても消えぬ母親の愛情ににている」と、亡き母を偲び、白いカーネーションを贈ったこと。
母の日にカーネーション。ちょっと素敵なチョイスに思えました。
一年に一度、照れくさくても言えるといいですよね。
「お母さんありがとう」
是非、予定してみてください。
花たより|2010月04月30日
水芭蕉(みずばしょう)に、こんな身近で出会えた事に驚き、とても嬉しく思いました。
水芭蕉(みずばしょう)といえば、まず思い浮ぶのが、群馬県の尾瀬ですが、岐阜県でも郡上白鳥に群生地があり有名ですよね。私が出会った場所は、東白川村の中でも、山奥の静かな湿地でした。

案内して下さった方によると、これでも昨年より花は増えているとのことでした。まだまだ未完成な感じですが、これが、自然の水芭蕉(みずばしょう)の姿と、思って頂ければ嬉しく思います。
水芭蕉の根茎は毒性が強く、ツキノワグマは、冬眠後に体内の老廃物などを排出するための下剤として食べるといわれています。と、いうことは、水芭蕉のあるところに、熊が出没するということでしょうか・・・
花が終わると1mぐらいに大きく伸びる葉が芭蕉(バナナの仲間で背の高い木)に似ていて、かつ、水辺に生えるので付いた名前だということです。
仏炎苞(ぶつえんほう)とよばれる白いものは花でなく葉っぱで、本当の花は中心部の棒のような所に密集している薄緑色の小さなものです。
花言葉は「美しい思い出」「変わらぬ美しさ」「浄化」です。
水芭蕉にぴったりの花言葉だと思いませんか?!
特に、ツキノワグマの話で「浄化」は納得してしまいました。
毎年静かに見守っていきたい愛おしい花だと思いました。
花たより|2010月04月27日
昨年、その花を見かけた場所は、いつもの行動範囲より少し山奥ですが、登って行きました。
ちょっと薄暗い場所ですが、少し高い所で真っ白に咲くその花は、遠目からでも、すぐ見つけることができました。
得した気分で嬉しく、早足で近づきました。

大亀の木(おおかめのき)です。
初めて見た時は、白い額紫陽花(がくあじさい)かと思いました。
が、よくよく見ると、葉っぱが違いました。
葉脈が深く皺がよく目立ちます。
この葉が、亀の甲羅に似ていることから付いた名前だそうです。
そして、もうひとつの名前が虫狩(むしかり)…葉によく虫がつくので「虫食われ」が訛ったという説もあるそうです。
なかなか人目に付くことのないような山の中で咲いているので、お目にかかるチャンスがないかもしれませんが、是非、見て欲しいお勧めの花です。
花言葉が憎いですね…「黙っていても通じる私の心」ですって!!


![木の家・木造注文住宅の建築・施工を建築士・工務店と共にフォレスタイルがサポートします[岐阜県 愛知県 名古屋市 三重県など]](https://www.forestyle-home.jp/wp/wp-content/themes/forestyle/img/blog_head_title.jpg)