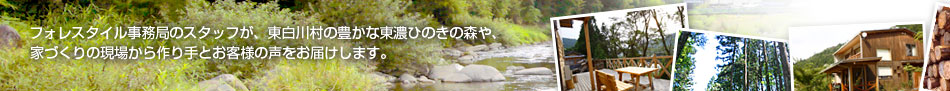花たより|2010月06月15日
梅雨入りしましたが、本日の東白川は朝から晴天です。
午後から、雨が降るとの予報ですが・・・
散歩の途中、道端で見かけた花です。
物忘れのひどい私ですが、先生に教えていただいた花の名前と由来が、すぐ頭に浮かんできました。

浮かんだ名前が、忍冬(にんどう)です。
冬の寒さに耐え忍び、この時期に花が咲く姿から付いた名前で、漢名だということです。
他にも呼び名はあります。
吸葛(すいかずら)は、和名で、一般的な呼び名がこれですね。
甘い蜜を吸う葛という意味から付いたそうです。
「忍冬」と書いて「すいがずら」と読ませる場合もあるとか。
3つ目の呼び名が、金銀花(きんぎんばな)。
咲き初めは、白い花が徐々に黄色くなり、一つの枝に白い花と黄色い花が同居していることから付いた名前です。
3つも呼び名がありますが、どれもうなずけてしまいます。
草のように見えますが、吸葛(すいかずら)は、常緑のつる性低木です。
華やかさはあまり感じられませんが、1箇所から2つの花が咲いているのがユニークで、花の形もおもしろいと思いませんか?!
近づいてみると、良い香りがしました。
花言葉は、「愛の絆」。
今回も「愛」絡みの花言葉でした。
おまけの1枚も是非ご覧になって下さい。

お知らせ|2010月06月14日
先日、完成が近いお施主様を訪問しました。
あれこれとお願いやら相談やらに伺い、完成への想いを聞いてまいりました。
現場は、ウッドデッキ施工と庭の再生の最中でした。

私は、現場に足を運ぶのは久しぶり。
写真では経過をみていたものの、現物はやはり圧倒されるほどの存在感と美しさ。
私が住むわけでもないのに、うっとりするやらこの先の仕上がりが気になるやら、完成がますます楽しみになり心弾むひと時でした。
庭の隅で成り行きを見つめるたぬきもうれしそうだったので、失礼してパチリ。

また、見学会をお願いしたところ、快く承知していただけたので皆さんにも御案内ができそうです。
どうぞお楽しみに。
花たより|2010月06月11日

友だちの家の庭先に咲いていた大山蓮華(おおやまれんげ)です。
噂通り、6月の最初に紹介した朴の木の縮小版で、花も葉もよく似ています。
ただ、違うところは、花が少しうつむき加減に咲いているところでしょうか!?
真っ白な蕾がとてもかわいらしく、花弁が開くと赤っぽい雄しべと黄色の雌しべが、出てきました。
色のコントラストが、ステキです。
大山蓮華(おおやまれんげ)という名前は、山に咲く蓮(はす)に似た花(華)より由来しているとのこと。
群生している花見たさに、遠くの山まで出かける人が多いと聞きます。
「天女花」と呼ばれる上品な美しさを持つ大山蓮華(おおやまれんげ)に魅かれることに、うなずけます。
花言葉「変わらぬ愛」
忘れてはいけない言葉ですね。
花たより|2010月06月08日
林の中で自生しているのを見て欲しくなり、知り合いから分けて頂いたのが、二人静(ふたりしずか)と、いう花です。

ステキな名前ですが、調べてみたら、実は奥の深い話がありました。
二人静(ふたりしずか)の名前の由来は、能楽「二人静」に由来していると言われています。
若菜摘みに出かけた乙女に静御前(源義経が愛した女性)の霊がのりうつり、乙女が舞い始めると静御前の亡霊が姿を現し乙女に寄り添いながら二人で舞う。というのが簡単なあらすじです。
2本の花穂の先に米粒のような白い花をつけるという花の姿を「二人静」の舞姿にたとえたということでしょうね。
ひっそりと仲良く寄り添うように咲いている花だと思っていましたが、一つが亡霊だなんて…
花穂が3本や4本の時もありますが、その場合は亡霊が増えるのでしょうか?!
二人静(ふたりしずか)の花言葉は「いつまでも一緒に」
花言葉に、我が家もあやからねば…
ちなみに某老舗銘菓のちょっと甘くて品の良い小粒の和菓子、「二人静」は、『ににんしずか』と読むのだそうです。
花たより|2010月06月04日
問題です!!
この木に咲く花の名前は?

ヒントその1 木は大きくなります。
ヒントその2 果実は皆さんも、よくご存知のおいしいお菓子になります。
ヒントその3 お相撲さんの名前にも、あったような…?!
さあ、皆さん、おわかりですか?
答えは、栃の花(とちのはな)です。橡(とち)とも書くそうです。
一つ一つの花と花弁は大きくないのですが、雄しべが伸び大きく目立つ花です。
花の付き方が、おもしろいと思いませんか?
長い5枚の葉も特徴がありますよね。
小学校の国語の教科書にも採用されている、児童文学「モチモチの木」に登場する木がこの栃(とち)の木です。
花言葉は「ぜいたく」
心は、豊かでぜいたくでありたいですね。
花たより|2010月06月01日
皆さんは朴の葉を使った郷土料理をご存知ですか?!
朴葉寿司、朴葉餅、朴葉味噌・・・今回は葉ばかり重宝され、忘れられがちな朴の花(ほおのはな)を紹介したいと思います。

間近で花を見ることができない程、朴の木は大きいのですが、ラッキーなことに、近くでお目にかかることができました。
朴の花(ほおのはな)の大きさは日本の野生植物では、最大だと言われています。
大きな葉に乗るようにして咲く花は、ちょっとグロテスクな赤っぽい花芯と艶やかな厚みのある8~9枚の花弁で成り立っています。
花弁のやさしい色合いがとても気に入りました。凛とした花の姿が葉に負けないと主張しているようで、たのもしくも感じました。
甘い香りを放つと聞いていましたが、わからず仕舞いだったのが残念でした。
驚いたことに、朴の花(ほおのはな)は、神様の好きな花だとか。私も初めて知りました!!
花言葉は「誠意ある友情」
フォレスタイルも日々こんな気持ちで取り組んでいます。
その他, 東白川村便り|2010月05月28日
今日もランチの公開です。
今、話題の「穀楽(ごくらく)細うどん」をいただきました。
これは、今月16日に岐阜県の可茂地区B級グルメ「かも1」というイベントが開催され、そこでグランプリを獲得したものです。
なんでもイベントの後、このうどん販売元には通常の300倍のアクセスがあるとか。
昨日そんな話を聞いて興味を持っていました。
それが、フォレスタイル事務局のお隣で食べられるとの情報をキャッチ。
早速注文し、いただいてみました。

さて、感想はというと。
お茶の生葉がのっていて見た目もさわやか。めんつゆのいれものは竹筒。いい雰囲気です。
お味は…。お茶が米粉に練り込んでありもちもちした食感で後味ひく美味しさ。
お隣のレストラン味彩では、めんつゆでいただくものですが、サラダ風にしてもよいようです。
話題の商品をいち早く食せたことに大満足!
が、お腹がグーグー鳴っていた私の空腹への満足感はいまひとつといったところでした。
日替わりランチメニューになって、朴葉寿司やスイーツなんかが付くといいよね~とあれこれ批評をしながらの、ランチとなりました。
今日御紹介したのは「ごくらくうどん」でしたが、冬場には「じごくうどん」なるものがお目見えするとか。今から楽しみです。
みなさんも来村された際には是非お試しください。
花たより|2010月05月28日
公園や庭木に植えられ、お馴染みの花です。
鈴のような花の形の可愛らしさと、色のやさしい雰囲気が、気に入っています。

灯台躑躅(どうだんつつじ)と同属植物ですが、総状花序(注1)であることと、ピンクのラインがあることで区別されているのが更紗灯台(さらさどうだん)です。
花冠の縦縞を更紗模様に見立て、付けられた名前です。
別名は、風鈴躑躅(ふうりんつつじ)と言われていますが、写真を見れば「なるほど!」と納得できますね。
花言葉は「喜びあふれ」「明るい未来」
五月晴れの空の下で、眺めていると、思わず顔も緩み、優しい気持ちになれました。
そうそう、更紗灯台(さらさどうだん)は秋の紅葉も見事ですよ。
注1・・主軸が長く伸び、柄のある花が間隔をあけてたくさん着いているもの。
その他, 東白川村便り|2010月05月27日
恥ずかしながら、今日の私のランチを公開します。
私はお弁当派なのですが、今日のメニューはこれ。
御存じの方もあると思いますが「朴葉寿司(ほうばずし)」です。

葉が開く今頃から夏場にかけて、東白川村ではよく食卓に上ります。
朴の木は、事務所の周りにもたくさんあります。

山に朴の葉が揺れ始めると、このあたりではマスやサバの酢づけが店頭に並びます。
中にいれるものには、家庭の味がありさまざまです。
先日いただいたものには「蜂の子」が入っていました!
味はもちろんのこと、主婦にはありがたい季節メニューです。
何と言っても食器洗いが不要なこと。
葉の殺菌作用で保存も可能ですし、食べ終わったら葉は自然にお返しできる。
作っておけばいつでも好きな時に食べられる。
多忙な農繁期に備えての先人の知恵だったのだと思います。
田んぼの畦で食べるのが昔の常だったでしょうが、パソコンの前で食べるのも悪くないですよ。
「いただきまあ~す」!」
花たより|2010月05月25日
今の時期、新緑の山をバックに、薄紫色の花が浮きだって咲いているのをよく目にしますが、皆さんは気付かれたことありませんか?
高い所で咲いているので、分かりづらいかもしれませんが、桐の花(きりのはな)です。

桐の花(きりのはな)は、小さい種子が風で飛び、発芽率が高いうえ、成長が早いので、東白川では、至る所で野生化したものが見られます。
桐の木は大きく、花を近くで見ることが難しく、私も今回写真に収めるのに苦労しました。
枝先に集団で上向きに咲いていますが、一つ一つの花は、やや下向きで咲き、大きさは、5~6センチ程、花弁は5枚です。遠くで見るより、花色は薄く、花色から気品を感じました。
中国原産の桐は古くから、湿気を通さず、割れや狂いが少ないという事で、良質な木材として、重宝されてきました。
また、日本国内で生産される木材としては、最も軽いということも特徴です。
桐(きり)の花言葉は「高尚」。
高級家具の代名詞になっているだけあって、ぴったりの花言葉ですね。


![木の家・木造注文住宅の建築・施工を建築士・工務店と共にフォレスタイルがサポートします[岐阜県 愛知県 名古屋市 三重県など]](https://www.forestyle-home.jp/wp/wp-content/themes/forestyle/img/blog_head_title.jpg)